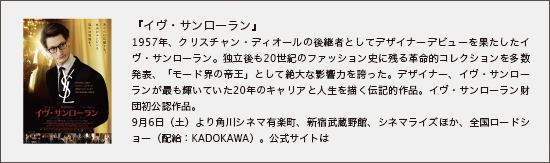2014/08/07
MOVIE: YVES SAINT LAURENT
若き天才デザイナーの人生を彩った、光と影を描いて

フランス・モード界の伝説的存在といえば、イヴ・サンローランだ。サンローランの公私に渡るパートナー、ピエール・ベルジェとの関係を軸に、サンローランの1957年~1976年までの半生に迫る伝記映画『イヴ・サンローラン』が日本でも公開される。天才と謳われたデザイナーの華麗なキャリア、喝采と孤独の日々、そして創造の苦しみの中で追い求め続けた、永遠のエレガンスが描かれる。
text by Ryoko Kuraishi
弱冠21歳でクリスチャン・ディオールの後を継ぎ、トップメゾンを率いるデザイナーとして彗星のごとくデビューしたイヴ・サンローラン。極端に内気で人嫌い、デザイン以外は何もできない、ガラスのハートを持った青年だった。ファッションには疎いが文学と絵画に精通し、若い芸術家を支援している26歳のピエール・ベルジェと出会ったのもこの頃のこと。2人はすぐさま恋に落ちた。イヴの才能を見込んだピエールは、プライベートはもちろん、ビジネス面でも彼の支えとなることを決意。クリエイション以外のすべての雑務を引き受け、以後数十年に渡るパートナーシップがスタートする。
そんなピエールの献身的なサポートもあり、イヴは26歳で自らのメゾン<イヴ・サンローラン>を設立することができた。"モンドリアン・ルック""スモーキング""サファリ・ルック"など、モード界の伝説となったコレクションを次々と発表して、一躍「モード界の貴公子」ともてはやされるようになる。そんな栄光の日々のなか、神経衰弱を繰り返し、徐々に疲弊していくイヴ。スターデザイナーとして肩にのしかかるプレッシャーは堪え難く、安定したピエールとの暮らしにも息苦しさを覚え、次第に薬物やアルコールに溺れるようになっていく。
監督は、映画『パリ、ただよう花』などで俳優としても活躍するジャリル・レスペール。「クラシックで強烈な恋愛映画を撮りたいと思っていた」と自身がインタビューで語っているように、これはイヴとピエールの美しい恋の物語である。そしてまた、自身の理想を追い求めて苦闘する天才と、才能豊かなアーティストを支える人間が織りなすヒューマンドラマでもある。
「これはファッションの世界の話ではあるけれど、それはあくまでバックグラウンドで、できるだけファッションとは切り離して考えたかった。僕が惹かれたのはイヴ・サンローランのクリエイションに対する姿勢、ほとんどアーティストと言えるような地点に到達した彼のあり方だから。自分の夢のために苦しみながらも創造する必要性、そのクリエイションによってさらに自分が苦しくなる。そんなパラドックスを描きたかった。そしてそんなクリエイターを支える人々の姿を描くことにも惹かれていた」

絢爛豪華に画面を彩るアーカイブの数々と、華やかな人間関係
主役のイヴを演じたのはコメディ・フランセーズ(フランスの国立劇団)出身のピエール・ニネ。端正な容姿を、若き日のイヴそっくりに作り込んで撮影に臨んだ。その役作りはピエール・ベルジェその人に、「本人じゃないかと思い、動揺して混乱した」とまで言わせたほど。一方、ピエール役を好演したギョーム・ガリエンヌもコメディ・フランセーズ出身。監督、主演を務めた映画『ママン』が今年のセザール賞を受賞するなど、フランスでいま、最も注目を浴びている役者の一人である。
もう一つの見どころは、スクリーンに次々と現れるイヴ・サンローラン財団所有の貴重なアーカイブの数々だろう。ピエール・ベルジェ本人の全面協力により実現したこの映画には、財団が所有・管理する美しいドレスや宝飾品、おびただしい量の直筆のスケッチが小道具として登場する。またコレクション会場となったインターコンチネンタルホテル(現在のウェスティン・パリ)やメゾンのアトリエ、マラケシュの別荘なども、60年代、70年代の雰囲気そのままに再現されている。
イヴを取り巻く人々も華やかだ。オートクチュールコレクションのフロントロウには『ハーパース・バザー』誌の名物編集長カーメル・スノー。スモーキングを着こなし、アンドロジナス的な魅力を振りまいたモデル、ベティ・カトルー、後年はジュエリー・デザイナーとしても活躍したルル・ド・ラ・ファレーズら、イヴの遊び仲間でもあるミューズたち。そして愛人ジャック・ド・バシェールをめぐる宿命のライバル、カール・ラガーフェルドとの関係。モードの世界の裏側の華やかな人間関係も、丹念にすくっていく。とはいえ、そこに描かれているのは愛情、嫉妬、誘惑、情熱......。私たちと何ら変わらない、生々しくてむき出しの感情の一つひとつなのだけれども。