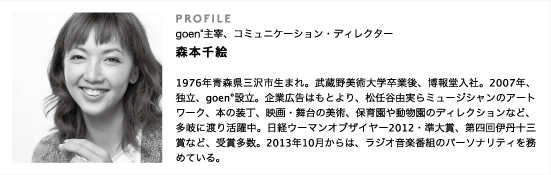2013/12/12
INTERVIEW: CHIE MORIMOTO

日本のクリエイティブ業界を牽引するコミュニケーション・ディレクター、goen°主宰の森本千絵さん。広告デザインやCM映像制作の枠を超えた活動は常に注目を集めています。現在、森本さんが手掛けた松任谷由実さんの新アルバム『POP CLASSICO』のジャケットデザインの世界観が、バーニーズ ニューヨークでも独自のクリエイティビティで表現されています。『POP CLASSICO』のお仕事について、ご自身と音楽との関わり方について、またバーニーズ ニューヨークについて、森本千絵さんにお聞きしました。
―バーニーズ ニューヨークに対して、どのような印象をお持ちでしたか?
元々客としてお店に行ってました。好きなブランドも入っていますし、プライドを持ってセレクトしている姿勢が信頼できるので、たまにお買物させていただいています。特に銀座店は銀座グラフィックギャラリーで展示を行っていた時期もあったので、ウィンドウディスプレイをはじめ、グラフィックの世界と一緒に何かやれたら面白そうだな、と思いながら拝見していました。今回はレスリーとの縁を介してたまたまコラボレーションの機会を得た形です。
―松任谷由実さんとの出会いについて、教えてください。
由実さんに初めてお会いしたのは、2012年の夏、NHK教育テレビジョンの『ユーミンのSUPER WOMAN』という番組でした。由実さんと一緒に古本屋さんへ行き、景教とその文化について教えていただいたり、フランスの人が描いた妖怪の本などを見たり、一緒に高野山へ行って曼荼羅を見たりしました。そんな中で由実さんから"懐かしい未来"という言葉が出て来て、それが凄く面白いと思いました。"懐かしい未来"をわかりやすく形状で伝えるのには、海の中や自然物などを用いました。植物などもそうですが、そのラインを手で描こうなんて難しすぎるんです。目指しても目指しきれない未来のデザインは、実は元々生まれたときに傍に在るものだとも思います。生まれたときがいちばん最高の未来なんじゃないかと思ったりもします。そんなことを、由実さんと一緒に高野山を歩きながら思ったり話したりしていました。
―具体的に松任谷由実さんとお仕事をすることになったのは、どのような経緯でしたか?
由実さんが40周年を迎えた2013年のお正月の新聞広告を担当させていただきました。そのときには、もうすでに"懐かしい未来"というキーワードで何枚かコラージュを作り始めていたんです。由実さんのイメージには、和と洋もそうですし、懐かしいものと現実世界ではあり得ないような未来的なもの、満ち溢れるような生きる喜びと、生きていくことが辛いのを慰めるような気持ちなど、さまざまなものを全部コラージュしていくことが合うと思いました。悲しい人でも、喜びを持った人でも、同じ楽曲を聴いて各々が自分の歌だと思えるのが、ユーミンの物凄いところだと思うのです。『POP CLASSICO』は「ポップ」と「クラシック」というキーワードから成り立っていますが、由実さんと出会ったときから、まさにこの一年はそのようなテーマで由実さんと接していましたので、最初、松任谷正隆さんから、『POP CLASSICO』というキーワードを伺ったときには、仕事として初めての依頼であるにも関わらず自分には懐かしいというか、由実さんに個人的に会ったときからずっと思ってきたことだったので、ポンッと形にしやすかったですね。

―今回の『POP CLASSICO』のジャケットもそうですが、音楽の仕事に取り組まれるときのことをお聞かせいただけますか?
私は元々、CMや新聞広告をたくさんやっていましたが、社会人7〜8年目の頃にミスターチルドレンやゆず、坂本美雨さんなど手掛けるようになりました。「音楽から企画を考えるというのは、物凄く自然だな」と思ったのはこのときです。音を聴き込んで体に憶えるから、音楽は嘘が無い。体が音楽を憶えて、体が勝手に出歩いてパッてアイデアに出会うわけでしょう? 頭で音楽を処理して説明しているのではなくて、ちゃんと体を通しているから物凄く自然だと思いました。それからは<組曲>などの企業広告、CMにしても保育園の空間作りにしても、いつもイメージに合う十数曲のサウンドトラックを先に作って取り組むようにしています。そういう仕事の仕方に切り替わってから、7年経ちます。入社して8年で博報堂を辞めて、goen°を立ち上げ今年で7年目なので、キャリアとしては15年目。「言葉」から企画を作っていた時期が8年、「音」が無いと企画が作れないという風になってから8年目、ちょうど半々になりますね。今回の『POP CLASSICO』はその集大成と言えます。
また今回の由実さんとのお仕事は、そもそも信頼してくださる形から違いました。『POP CLASSICO』の世界観を作り出すパートの一人として迎えられ、例えばストリングスならこの人、ベースならこの人というように、絵を作るパートの一人として信頼してくださいましたし、それに応えられるくらいに、最初の段階で今回のアルバムに込めた想いをわかりやすく伝えてくださったので、凄く一緒にセッションがしやすかったです。
―ご自身でつくられた『POP CLASSICO』を改めて今ご覧になって、どのようなことを感じられますか?
このデザインは『POP CLASSICO』という言葉と、深海のようなユーミンの世界にどっぷりと潜っていったら、物凄くいっぱい生命が発見されたというものです。お母さんのお腹の中に潜り込んでいったら、未来の自分の種が居たような感じ。今目に見えているものより、さらにたくさんの色や生命が目前にグワーッと広がっているんだよ、と見つけられた旅になりました。絵を描いたり、コラージュしていて凄く気持ち良かったし、休憩も取らずトイレにも行かず、一気に描き上げました。終わったあとも神経が張って全然眠れなくて、ミュージシャンの方によればそれはライブ直後のミュージシャンの精神状況と同じなのだそうです。もう一回やれって言われても、どうやってやったか全然憶えていないし、コラージュもどのような順番でハサミを入れたか全く記憶に無いので、急に状況が変わって、「やっぱりほかのアルファベットも全部作ってください」と言われたらどうしよう?と思っていました。これは『POP CLASSICO』で完結している、このときしか作れないものだったんです。
―大きな仕事を達成されたあとですが、今後、達成されたい夢はありますか?
ジャック・ロンドンという、40歳で亡くなった小説家がいるのですが、彼の書いた『火を熾す』という短編小説の映画を作りたいです。いま徐々に準備をしています。ただ男が生きて、火を熾して、死んでいくという話なのですが。
私がもっとも制作意欲を掻き立てられるのは、血がすり切れるくらい、必死に生きている人の姿を見たときです。例えば(ゆずの)北川くんの結婚式でユーミンが歌ったのですが、体調不良で声が出ない状況の中、必死に歌っていて、喉が痛そうで、目からぼろぼろ涙も出ているのだけど、最後まで歌っている姿を生で見たのは初めてでした。高野山へ行った時もそうですが、とんでもなく必死で、全ての感受性をもって全力で生きている姿が非常に格好いいんです。痛いくらいのその生命力に惚れています。私はそれをそのまま形にしているんです。ジャック・ロンドンの話は、正にそういう話です。不器用でもなんでも良くって、その人から発せられるオーラが凄ければ、私も作りたくなるし、仕事をしていてとても楽しいです。
―では最後に、バーニーズ ニューヨークのお客様に向けたメッセージをお願いします。
バーニーズ ニューヨーク自体にも、『POP CLASSICO』的な要素がありますよね。世の中の流行がこう来ているからこう、というような解釈ではなく、いいものをきちんと自分たちの眼でセレクトしている感じがします。若手デザイナーブランドの取り扱いにしても、一つひとつの理由がしっかりしているというか、そのブランドのどこが好きなのか、意志が見えるセレクションだと思います。それぞれが高めあっていい「気」が満ちているので、高校生くらいのときにはその独特の「気高さ」に気後れしてしまったくらい。それが先日は、由実さんとのお仕事を経てまた変化があったのか、フッと自然に感じていろいろと買ってしまいました(笑)。バーニーズ ニューヨーク特有のプライドは、とてもいいものだと思います。
* * *